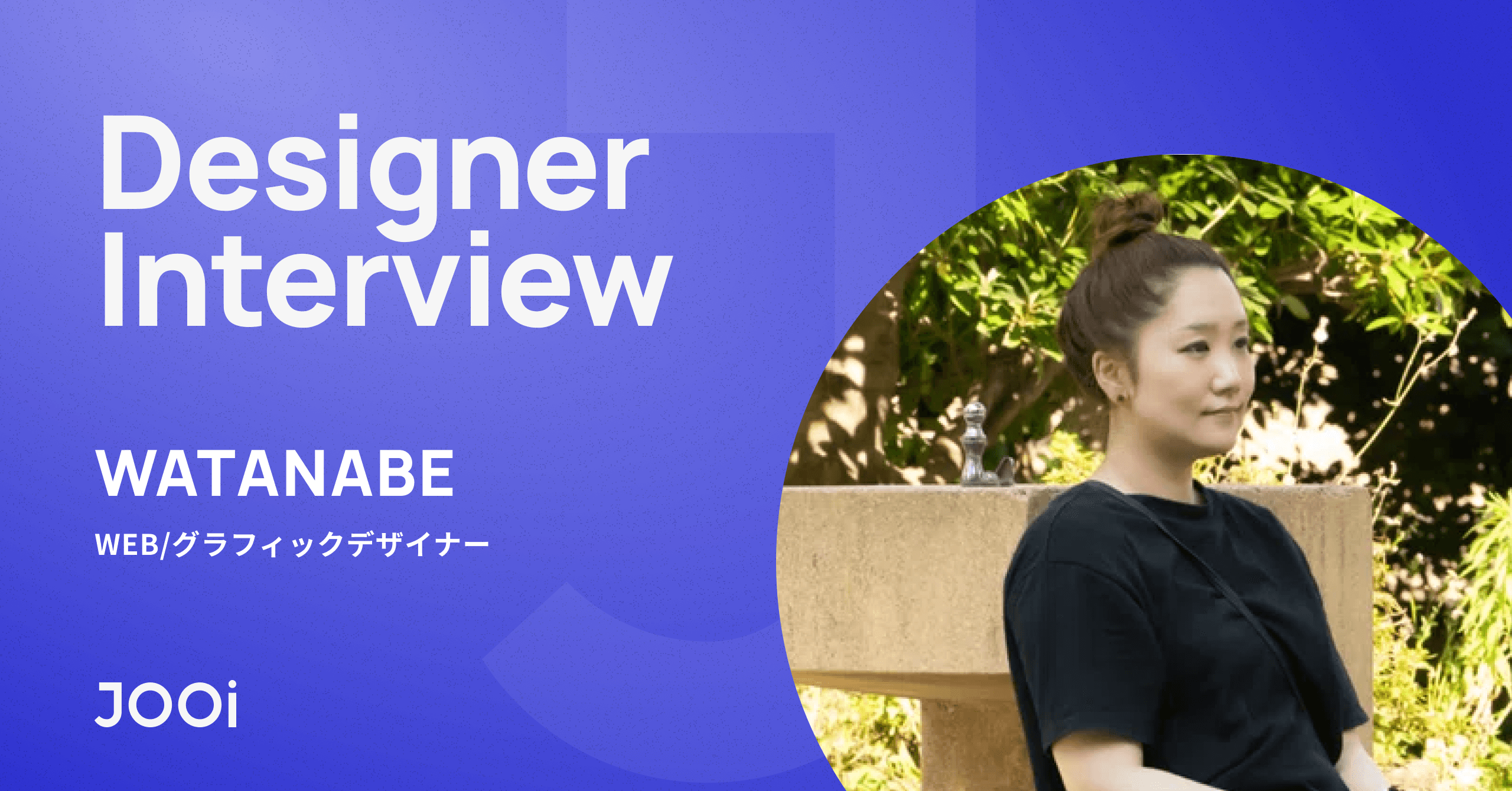UI/UXデザイナー
【JOOiデザイナーインタビュー】0→1からグロースまで推進するUI/UXデザイナー Kumanoさん
投稿日:
2025/09/15
今回ご紹介するのは、0→1の立ち上げからグロースまで、一貫して推進してきたUI/UXデザイナーのKumanoさんです。
課題を論理的に整理し、データとユーザーの声を組み合わせて検証を進める力。そして役割にとらわれず、チーム全体を前に進める推進力を持つデザイナーでもあります。
本記事では、Kumanoさんのキャリアや実務での進め方、デザインに対する考え方をインタビューをもとにまとめました。
スキルアップやキャリアアップを目指すデザイナーはもちろん、スタートアップや新規事業に携わる方にも参考になる内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
キャリアについて
略歴

私は東京大学大学院で都市計画や交通工学を学び、在学中に仲間と起業し、いくつかのサービス立ち上げを経験しました。
その後、不動産系のスタートアップに転職し、一人目のデザイナーとしてアプリの改善やリニューアルを担当しました。さらに製造業向けのSaaSの立ち上げにも携わり、現在は大手SaaS企業で勤務しながら、スタートアップの支援も行っています。
大学院を中退してさまざまな事業を起業
研究を続けても、自分がどんなキャリアを歩むのかが見えませんでした。そんな時に同級生から「一緒に会社を立ち上げないか」と声をかけられ、挑戦を選びました。大学院を休学し、最終的には中退という決断をしましたが、「課題を形にする」体験の方が自分には価値がありました。
起業中は、飲食・観光・教育など身近なテーマで0→1を何度も繰り返しました。結果が出ないことも多く、無給で厳しい時期もありましたが、ユーザーの課題を見つけ、仮説を立てて検証し、学習して次に生かす。この一連の流れを体に染み込ませることができました。途中で、外部環境の変化に合わせて早めに方向転換したこともあり、意思決定の速さと柔軟性の重要さを強く意識するようになりました。
不動産からSaasまで一人目デザイナーとしてキャリアを広げてきた道のり
自分の強みや弱みを知るために、不動産系スタートアップへ転職しました。最初は小さなUI改善から始め、やがて全画面を見直して文言や動作の揺れを整え、デザインシステムを構築しました。データで離脱ポイントを確認し、ユーザーインタビューで理由を探る。定量と定性を組み合わせて優先度を整理し、試作で早めに合意形成を進めました。その結果、ユーザー体験とコンバージョン率の改善につなげることができました。

次に挑んだ製造業向けSaaSでは、現場観察から最小限の試作品(MVP)を設計し、約3社で検証。その後有償化を経て10社規模まで導入を拡大しました。拡大フェーズでは業界ごとの違いと共通点を整理し、成長に耐えられるよう設計を再構成。ロードマップの策定、展示会での説明、フロント実装の補助まで担い、チームが成果を出せるよう幅広く動きました。
家庭環境の変化を機に、長く続けられる働き方を重視して大手SaaS企業へ。現在は既存プロダクトと新規事業の両方に携わり、限られた時間で最大のアウトプットを出すことを意識しながら活動を続けています。
実績紹介
不動産アプリのUIリニューアル

全体UIの改善 一人目のデザイナーとして参画しました。最初は細かいUI改善から始め、最終的に全画面を棚卸ししてUIを再設計しました。表記や挙動の揺れを洗い出し、コンポーネントの状態・間隔・タイポグラフィなどのルールを定義。ファネルで離脱が大きい箇所を特定し、インタビューで理由を確認して優先度を決めました。試作で認識を合わせ、実装と運用に負担がかからない形でリリース。体験の統一とコンバージョン改善につながりました。
製造業向けSaaSの立ち上げと拡大

プロダクトデザイン:開発した画面 製造業の見積業務に課題を見出し、現場観察からMVPを設計しました。まずは約3社で検証を行い、有償運用に移行。展示会や商談での説明にも入り、10社規模まで拡大しました。拡大フェーズでは、業界ごとの差異と共通項を整理して理想像を再定義。現在の制約では到達できないポイントを明確にし、デザインシステムをアップデートしました。優先度設計、ロードマップ、リリース管理までカバーし、必要に応じてフロント実装も補完しました。
AI系プロダクト群の最適化と新規事業
複数プロダクトが継ぎ足しで増えていた状態に入り、仕様とUIを棚卸しして重複と矛盾を解消。共通ルールを整えて再利用性を上げました。新規事業ではAIを前提に体験を設計。対話の前提や入力の粒度、自動化のタイミングなど、従来のUI設計とは異なるポイントを設計に反映しました。ClaudeやChatGPTで観点を広げ、Figma Makeでラフに形にすることで、検討の速度を上げました。
発揮するバリュー
チームを動かすために役割を超えて動く
私は肩書きにとらわれません。必要ならPdMの計画づくり、営業での説明、実装の補助まで自分が担います。
判断軸は「今、チームに必要なことは何か」です。時間ではなく成果で貢献します。ムダを減らし、短いサイクルで決めて、作って、確かめます。これが長く価値を出し続けるための前提です。
合意を早めて改善を再現できる仕組みを作る
最初に現場に入り、誰がどこでどのように困っているのかを把握し、簡潔に整理します。関係者が同じ前提で会話できるようにすることが出発点です。そのうえで、主要フローや例外を含んだプロトタイプを早い段階で用意し、抽象的な議論に時間をかけずに認識を合わせます。さらに、数字で「どこ」でつまずくかを確認し、ユーザーの声から「なぜ」を明らかにすることで改善の優先度を明確にします。最後に、そのプロセスを仕組み化し、誰が取り組んでも同じように進められる状態にすることで、継続的な改善を実現します。

立ち上げ期と成長期で進め方を変え、AIで生産性を高める
0→1のフェーズでは理想像を仮置きし、そこから引き算してMVPを早く出すことを重視します。スピード感を持って形にすることが、検証と学習を加速させます。グロースのフェーズでは、小さな改善を積み重ね、学びを残すことで次の判断に活かし、成果の再現性を高めます。また、AIは発想を広げたりラフ案を素早く形にしたりするために活用しますが、最終的な判断は必ず自分で行い、その根拠を明確にしています。
まとめ
Kumanoさんありがとうございます!Kumanoさんは、初期の整備から拡大フェーズの仕組み化まで、現場で使える方法で前進させるデザイナーです。
現場密着での課題定義、プロトタイプでの認識合わせ、定量×定性の検証、フィードバックの仕組み化。さらに、0→1とグロースで求められる動き方の違いを理解し、職域を越えて推進します。 限られたリソースでも再現性のある成果を求めるクライアントにコミットできるデザイナーです。
このようなクライアントにおすすめ
一人目デザイナーが不在で、短期間で体験と設計を整えたいクライアント
増えすぎてバラバラなUIや仕様を整理してルール化したいプロダクトチーム
B2B・業務改善SaaSで、MVPから有償化・拡大まで伴走してほしいクライアント
定量と定性の仮説検証のサイクルを素早く回したいチーム
最後までご覧いただきありがとうございます。 Kumanoさんへのご相談はもちろん、そのほかデザイン業務についてご相談がございましたらお気軽にこちらよりご予約ください。
一覧に戻る
Related interview
関連するインタビュー

UI/UXデザイナー
【JOOiデザイナーインタビュー】0→1からグロースまで推進するUI/UXデザイナー Kumanoさん
投稿日:
2025/09/15
今回ご紹介するのは、0→1の立ち上げからグロースまで、一貫して推進してきたUI/UXデザイナーのKumanoさんです。
課題を論理的に整理し、データとユーザーの声を組み合わせて検証を進める力。そして役割にとらわれず、チーム全体を前に進める推進力を持つデザイナーでもあります。
本記事では、Kumanoさんのキャリアや実務での進め方、デザインに対する考え方をインタビューをもとにまとめました。
スキルアップやキャリアアップを目指すデザイナーはもちろん、スタートアップや新規事業に携わる方にも参考になる内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
キャリアについて
略歴

私は東京大学大学院で都市計画や交通工学を学び、在学中に仲間と起業し、いくつかのサービス立ち上げを経験しました。
その後、不動産系のスタートアップに転職し、一人目のデザイナーとしてアプリの改善やリニューアルを担当しました。さらに製造業向けのSaaSの立ち上げにも携わり、現在は大手SaaS企業で勤務しながら、スタートアップの支援も行っています。
大学院を中退してさまざまな事業を起業
研究を続けても、自分がどんなキャリアを歩むのかが見えませんでした。そんな時に同級生から「一緒に会社を立ち上げないか」と声をかけられ、挑戦を選びました。大学院を休学し、最終的には中退という決断をしましたが、「課題を形にする」体験の方が自分には価値がありました。
起業中は、飲食・観光・教育など身近なテーマで0→1を何度も繰り返しました。結果が出ないことも多く、無給で厳しい時期もありましたが、ユーザーの課題を見つけ、仮説を立てて検証し、学習して次に生かす。この一連の流れを体に染み込ませることができました。途中で、外部環境の変化に合わせて早めに方向転換したこともあり、意思決定の速さと柔軟性の重要さを強く意識するようになりました。
不動産からSaasまで一人目デザイナーとしてキャリアを広げてきた道のり
自分の強みや弱みを知るために、不動産系スタートアップへ転職しました。最初は小さなUI改善から始め、やがて全画面を見直して文言や動作の揺れを整え、デザインシステムを構築しました。データで離脱ポイントを確認し、ユーザーインタビューで理由を探る。定量と定性を組み合わせて優先度を整理し、試作で早めに合意形成を進めました。その結果、ユーザー体験とコンバージョン率の改善につなげることができました。

次に挑んだ製造業向けSaaSでは、現場観察から最小限の試作品(MVP)を設計し、約3社で検証。その後有償化を経て10社規模まで導入を拡大しました。拡大フェーズでは業界ごとの違いと共通点を整理し、成長に耐えられるよう設計を再構成。ロードマップの策定、展示会での説明、フロント実装の補助まで担い、チームが成果を出せるよう幅広く動きました。
家庭環境の変化を機に、長く続けられる働き方を重視して大手SaaS企業へ。現在は既存プロダクトと新規事業の両方に携わり、限られた時間で最大のアウトプットを出すことを意識しながら活動を続けています。
実績紹介
不動産アプリのUIリニューアル

全体UIの改善 一人目のデザイナーとして参画しました。最初は細かいUI改善から始め、最終的に全画面を棚卸ししてUIを再設計しました。表記や挙動の揺れを洗い出し、コンポーネントの状態・間隔・タイポグラフィなどのルールを定義。ファネルで離脱が大きい箇所を特定し、インタビューで理由を確認して優先度を決めました。試作で認識を合わせ、実装と運用に負担がかからない形でリリース。体験の統一とコンバージョン改善につながりました。
製造業向けSaaSの立ち上げと拡大

プロダクトデザイン:開発した画面 製造業の見積業務に課題を見出し、現場観察からMVPを設計しました。まずは約3社で検証を行い、有償運用に移行。展示会や商談での説明にも入り、10社規模まで拡大しました。拡大フェーズでは、業界ごとの差異と共通項を整理して理想像を再定義。現在の制約では到達できないポイントを明確にし、デザインシステムをアップデートしました。優先度設計、ロードマップ、リリース管理までカバーし、必要に応じてフロント実装も補完しました。
AI系プロダクト群の最適化と新規事業
複数プロダクトが継ぎ足しで増えていた状態に入り、仕様とUIを棚卸しして重複と矛盾を解消。共通ルールを整えて再利用性を上げました。新規事業ではAIを前提に体験を設計。対話の前提や入力の粒度、自動化のタイミングなど、従来のUI設計とは異なるポイントを設計に反映しました。ClaudeやChatGPTで観点を広げ、Figma Makeでラフに形にすることで、検討の速度を上げました。
発揮するバリュー
チームを動かすために役割を超えて動く
私は肩書きにとらわれません。必要ならPdMの計画づくり、営業での説明、実装の補助まで自分が担います。
判断軸は「今、チームに必要なことは何か」です。時間ではなく成果で貢献します。ムダを減らし、短いサイクルで決めて、作って、確かめます。これが長く価値を出し続けるための前提です。
合意を早めて改善を再現できる仕組みを作る
最初に現場に入り、誰がどこでどのように困っているのかを把握し、簡潔に整理します。関係者が同じ前提で会話できるようにすることが出発点です。そのうえで、主要フローや例外を含んだプロトタイプを早い段階で用意し、抽象的な議論に時間をかけずに認識を合わせます。さらに、数字で「どこ」でつまずくかを確認し、ユーザーの声から「なぜ」を明らかにすることで改善の優先度を明確にします。最後に、そのプロセスを仕組み化し、誰が取り組んでも同じように進められる状態にすることで、継続的な改善を実現します。

立ち上げ期と成長期で進め方を変え、AIで生産性を高める
0→1のフェーズでは理想像を仮置きし、そこから引き算してMVPを早く出すことを重視します。スピード感を持って形にすることが、検証と学習を加速させます。グロースのフェーズでは、小さな改善を積み重ね、学びを残すことで次の判断に活かし、成果の再現性を高めます。また、AIは発想を広げたりラフ案を素早く形にしたりするために活用しますが、最終的な判断は必ず自分で行い、その根拠を明確にしています。
まとめ
Kumanoさんありがとうございます!Kumanoさんは、初期の整備から拡大フェーズの仕組み化まで、現場で使える方法で前進させるデザイナーです。
現場密着での課題定義、プロトタイプでの認識合わせ、定量×定性の検証、フィードバックの仕組み化。さらに、0→1とグロースで求められる動き方の違いを理解し、職域を越えて推進します。 限られたリソースでも再現性のある成果を求めるクライアントにコミットできるデザイナーです。
このようなクライアントにおすすめ
一人目デザイナーが不在で、短期間で体験と設計を整えたいクライアント
増えすぎてバラバラなUIや仕様を整理してルール化したいプロダクトチーム
B2B・業務改善SaaSで、MVPから有償化・拡大まで伴走してほしいクライアント
定量と定性の仮説検証のサイクルを素早く回したいチーム
最後までご覧いただきありがとうございます。 Kumanoさんへのご相談はもちろん、そのほかデザイン業務についてご相談がございましたらお気軽にこちらよりご予約ください。
一覧に戻る
Related interview
関連するインタビュー

UI/UXデザイナー
【JOOiデザイナーインタビュー】0→1からグロースまで推進するUI/UXデザイナー Kumanoさん
投稿日:
2025/09/15
今回ご紹介するのは、0→1の立ち上げからグロースまで、一貫して推進してきたUI/UXデザイナーのKumanoさんです。
課題を論理的に整理し、データとユーザーの声を組み合わせて検証を進める力。そして役割にとらわれず、チーム全体を前に進める推進力を持つデザイナーでもあります。
本記事では、Kumanoさんのキャリアや実務での進め方、デザインに対する考え方をインタビューをもとにまとめました。
スキルアップやキャリアアップを目指すデザイナーはもちろん、スタートアップや新規事業に携わる方にも参考になる内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
キャリアについて
略歴

私は東京大学大学院で都市計画や交通工学を学び、在学中に仲間と起業し、いくつかのサービス立ち上げを経験しました。
その後、不動産系のスタートアップに転職し、一人目のデザイナーとしてアプリの改善やリニューアルを担当しました。さらに製造業向けのSaaSの立ち上げにも携わり、現在は大手SaaS企業で勤務しながら、スタートアップの支援も行っています。
大学院を中退してさまざまな事業を起業
研究を続けても、自分がどんなキャリアを歩むのかが見えませんでした。そんな時に同級生から「一緒に会社を立ち上げないか」と声をかけられ、挑戦を選びました。大学院を休学し、最終的には中退という決断をしましたが、「課題を形にする」体験の方が自分には価値がありました。
起業中は、飲食・観光・教育など身近なテーマで0→1を何度も繰り返しました。結果が出ないことも多く、無給で厳しい時期もありましたが、ユーザーの課題を見つけ、仮説を立てて検証し、学習して次に生かす。この一連の流れを体に染み込ませることができました。途中で、外部環境の変化に合わせて早めに方向転換したこともあり、意思決定の速さと柔軟性の重要さを強く意識するようになりました。
不動産からSaasまで一人目デザイナーとしてキャリアを広げてきた道のり
自分の強みや弱みを知るために、不動産系スタートアップへ転職しました。最初は小さなUI改善から始め、やがて全画面を見直して文言や動作の揺れを整え、デザインシステムを構築しました。データで離脱ポイントを確認し、ユーザーインタビューで理由を探る。定量と定性を組み合わせて優先度を整理し、試作で早めに合意形成を進めました。その結果、ユーザー体験とコンバージョン率の改善につなげることができました。

次に挑んだ製造業向けSaaSでは、現場観察から最小限の試作品(MVP)を設計し、約3社で検証。その後有償化を経て10社規模まで導入を拡大しました。拡大フェーズでは業界ごとの違いと共通点を整理し、成長に耐えられるよう設計を再構成。ロードマップの策定、展示会での説明、フロント実装の補助まで担い、チームが成果を出せるよう幅広く動きました。
家庭環境の変化を機に、長く続けられる働き方を重視して大手SaaS企業へ。現在は既存プロダクトと新規事業の両方に携わり、限られた時間で最大のアウトプットを出すことを意識しながら活動を続けています。
実績紹介
不動産アプリのUIリニューアル

全体UIの改善 一人目のデザイナーとして参画しました。最初は細かいUI改善から始め、最終的に全画面を棚卸ししてUIを再設計しました。表記や挙動の揺れを洗い出し、コンポーネントの状態・間隔・タイポグラフィなどのルールを定義。ファネルで離脱が大きい箇所を特定し、インタビューで理由を確認して優先度を決めました。試作で認識を合わせ、実装と運用に負担がかからない形でリリース。体験の統一とコンバージョン改善につながりました。
製造業向けSaaSの立ち上げと拡大

プロダクトデザイン:開発した画面 製造業の見積業務に課題を見出し、現場観察からMVPを設計しました。まずは約3社で検証を行い、有償運用に移行。展示会や商談での説明にも入り、10社規模まで拡大しました。拡大フェーズでは、業界ごとの差異と共通項を整理して理想像を再定義。現在の制約では到達できないポイントを明確にし、デザインシステムをアップデートしました。優先度設計、ロードマップ、リリース管理までカバーし、必要に応じてフロント実装も補完しました。
AI系プロダクト群の最適化と新規事業
複数プロダクトが継ぎ足しで増えていた状態に入り、仕様とUIを棚卸しして重複と矛盾を解消。共通ルールを整えて再利用性を上げました。新規事業ではAIを前提に体験を設計。対話の前提や入力の粒度、自動化のタイミングなど、従来のUI設計とは異なるポイントを設計に反映しました。ClaudeやChatGPTで観点を広げ、Figma Makeでラフに形にすることで、検討の速度を上げました。
発揮するバリュー
チームを動かすために役割を超えて動く
私は肩書きにとらわれません。必要ならPdMの計画づくり、営業での説明、実装の補助まで自分が担います。
判断軸は「今、チームに必要なことは何か」です。時間ではなく成果で貢献します。ムダを減らし、短いサイクルで決めて、作って、確かめます。これが長く価値を出し続けるための前提です。
合意を早めて改善を再現できる仕組みを作る
最初に現場に入り、誰がどこでどのように困っているのかを把握し、簡潔に整理します。関係者が同じ前提で会話できるようにすることが出発点です。そのうえで、主要フローや例外を含んだプロトタイプを早い段階で用意し、抽象的な議論に時間をかけずに認識を合わせます。さらに、数字で「どこ」でつまずくかを確認し、ユーザーの声から「なぜ」を明らかにすることで改善の優先度を明確にします。最後に、そのプロセスを仕組み化し、誰が取り組んでも同じように進められる状態にすることで、継続的な改善を実現します。

立ち上げ期と成長期で進め方を変え、AIで生産性を高める
0→1のフェーズでは理想像を仮置きし、そこから引き算してMVPを早く出すことを重視します。スピード感を持って形にすることが、検証と学習を加速させます。グロースのフェーズでは、小さな改善を積み重ね、学びを残すことで次の判断に活かし、成果の再現性を高めます。また、AIは発想を広げたりラフ案を素早く形にしたりするために活用しますが、最終的な判断は必ず自分で行い、その根拠を明確にしています。
まとめ
Kumanoさんありがとうございます!Kumanoさんは、初期の整備から拡大フェーズの仕組み化まで、現場で使える方法で前進させるデザイナーです。
現場密着での課題定義、プロトタイプでの認識合わせ、定量×定性の検証、フィードバックの仕組み化。さらに、0→1とグロースで求められる動き方の違いを理解し、職域を越えて推進します。 限られたリソースでも再現性のある成果を求めるクライアントにコミットできるデザイナーです。
このようなクライアントにおすすめ
一人目デザイナーが不在で、短期間で体験と設計を整えたいクライアント
増えすぎてバラバラなUIや仕様を整理してルール化したいプロダクトチーム
B2B・業務改善SaaSで、MVPから有償化・拡大まで伴走してほしいクライアント
定量と定性の仮説検証のサイクルを素早く回したいチーム
最後までご覧いただきありがとうございます。 Kumanoさんへのご相談はもちろん、そのほかデザイン業務についてご相談がございましたらお気軽にこちらよりご予約ください。
一覧に戻る
Related interview
関連するインタビュー