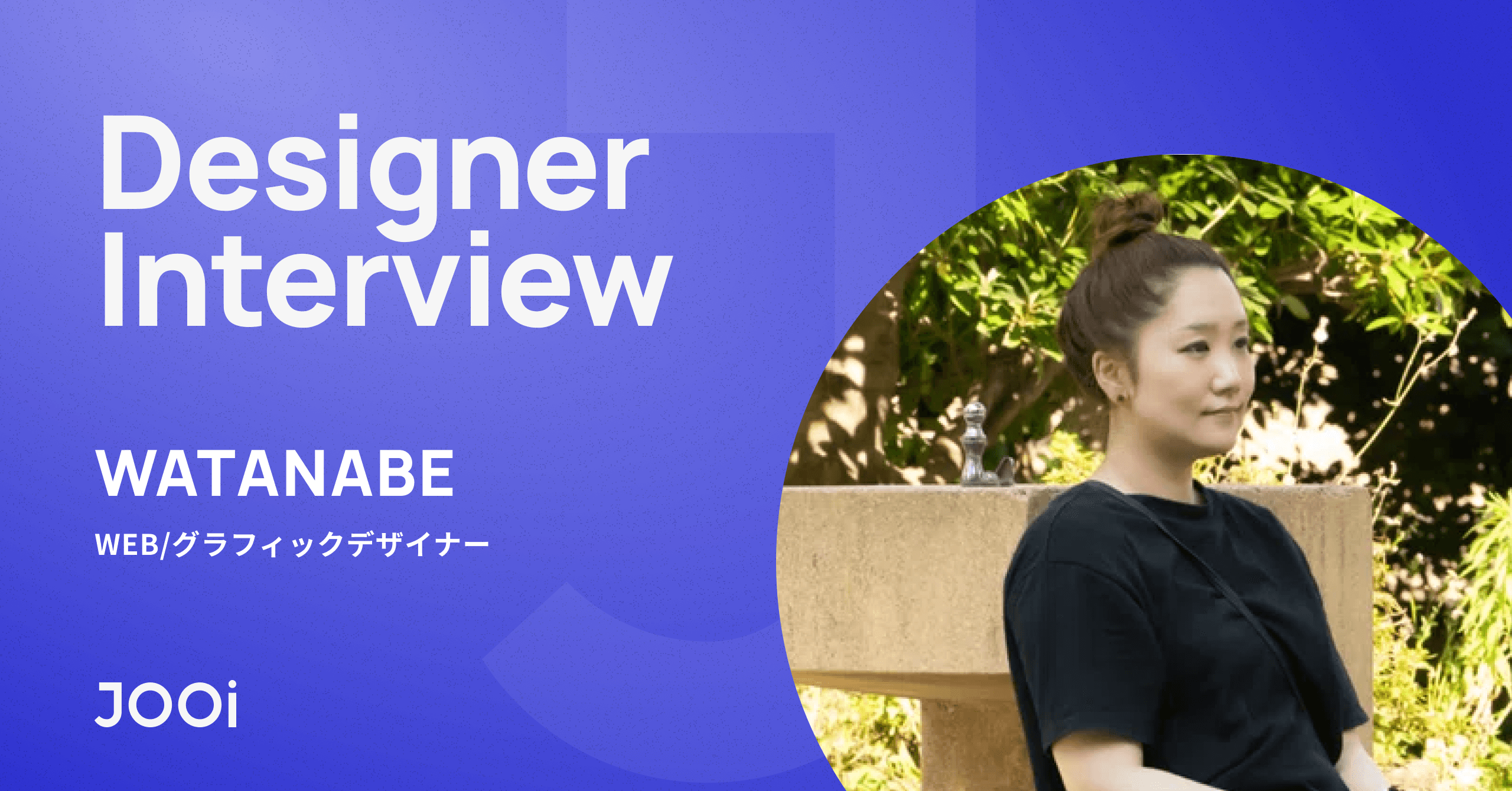クリエイティブディレクター
【JOOiデザイナーインタビュー】”相手の普通”を徹底し、成果に変えるデザインするIshibashiさん
投稿日:
2025/07/17
事業会社と代理店、両方を経験したIshibashiさんのブランド設計
本記事では、JOOiに在籍しているIshibashiさんをご紹介します。
Ishibashiさんは企業のビジョンや価値観といった抽象度の高い要素を言語化し、それをプロダクトやクリエイティブに落とし込んでいます。
ブランディングの上流工程から、UI/UX・マーケティング関連・コーポレート関連・営業関連など具体的なアウトプットまで、一貫してデザインを設計することができます。
このようなスキルや価値観がどういったキャリアで培われたのかなどインタビューの内容を本記事にまとめております。ぜひ最後までご覧ください。
1. キャリア
プロフィール

広告代理店、制作会社、事業会社と複数の立場を経験し、現在はフリーランスのクリエイティブディレクター/デザイナーとして活動しています。
過去には、月間1,500万PV・年商28億円規模のプラットフォームを運営する企業にて、マーケティング部長〜執行役員を歴任。ブランディング、UI/UX、コンテンツ企画、SNS運用まで、全体のコミュニケーション設計を担当してきました。
SaaS企業での展示会ブース設計やプロモーション設計、Web制作会社での事業部立ち上げなど立ち上げ・再設計フェーズに強みがあります。
現在は、スタートアップや中堅企業の“1人目デザイナー”として、ブランド戦略やプロダクト開発支援を中心に、多面的に関わっています。
現在行っていること
今は、フリーランスのクリエイティブディレクター/デザイナーとして、企業のブランド設計やUI/UXデザイン、マーケティング支援などをしています。スタートアップや中小企業の「1人目・2人目デザイナー」として入るケースも多く、ブランドの“ゼロイチ”を一緒につくるようなプロジェクトが中心です。
たとえば、「会社としてMVVはあるけど、それがビジュアルやトーンに落ちきっていない」とか、「営業資料とサービスサイトのトンマナがズレていて、社内外に一貫性がない」など、組織の中で「伝える設計」が曖昧になっている状態を整える、という仕事が多いです。
また、プロダクトに関わるだけでなく、展示会ブースやパンフレット、動画など「顧客とのタッチポイントすべて」に関与することも多いです。なので、ある意味「社外のクリエイティブ戦略室」みたいな立ち回りになることが多いかもしれません。
デザイナーを目指した理由
—アメリカでの幼少期の経験
「絵を描いたらお小遣いがもらえた」——これが僕の原体験です。
アメリカで小学生の頃、ノートの切れ端にロボットやキャラクターを描いて、それを友達にあげていたら、「これ、あげるよ」ってお菓子をくれたり、小銭をくれたりしたんです。完全に商売の意図はなかったんですけど(笑)
その瞬間、「あれ、これって価値になるんだ」って思ったんですよね。しかも、少しずつ“価格帯”が見えてくる。
人気キャラクターは高い、オリジナルはちょっと安いとか。
自分で何が売れるかを観察して、単価を決めて、納期を守るみたいなことを、今思えば自然にやっていた。その時の感覚は、今の「ブランド設計」に直結していると思います。
事業会社と代理店の違い
—“広く浅く”と“深く長く”——デザイナーとしての両面の学び
代理店と事業会社、どちらも経験してみて、やっぱり立ち回り方はだいぶ変わったなと思います。
代理店は、いろんなプロジェクトに横で関わるようなイメージですね。幅広く、いろんな業界・案件をスピード感もって触っていく感じでした。とにかくアウトプットを出すことが前提で、提案の質やスピードが求められていたと思います。
一方で、事業会社では縦に深く入っていくことが求められました。 僕がいた会社では、一つのサービスに対して営業、インサイドセールス、マーケ、開発、経理まで、本当にたくさんの部署と連携しながら動いていました。
そこで実感したのは、「これは誰の視点を通すべきか」とか「どこを説得すればプロジェクトが前に進むのか」というバランス感覚の大切さです。
言ってしまえばちょっと“政治的”な配慮も必要になってくる。 いろんなステークホルダーのことを考えて、みんなに納得してもらえる形にしていくというのは、インハウスだからこそ身についた感覚だと思います。
それぞれに良さがあって、どちらが正解という話ではないんですが、今の自分がフリーランスとして関われているのは、両方の経験があったからだなと思っています。
2. 制作物・実績
これまでたくさんのプロジェクトに関わってきました。今回はその中でも印象に残っている実績を具体的に2つ紹介させてください。
1つは、あるSaaS企業での展示会ブースの設計。もう1つは、大手飲料メーカーと立ち上げたオウンドメディアのデザインです。
展示会ブース
見せるデザインではなく、“成果を出す空間”をつくる
展示会の目的は、言うまでもなく「リードを獲得すること」です。
僕が関わったプロジェクトでは、月間300〜400件のリード獲得をKPIとして掲げていて、展示会ごとに何百件という成果が求められる状況でした。

当時、社内にはまだブース設計の専門部署はなく、マーケティング担当者と2〜3名でチームを組んで、構成・導線・演出・動画・パンフレットなど、すべてをゼロから設計しました。
特にこだわったのは、“現場でPDCAを回せる設計”です。
たとえば、ブース内の机やディスプレイの位置はすべて可動式にしました。
展示会1日目の終わりに「ここ、全然立ち止まってもらえないよね」「この角度、営業が声かけづらいね」といった声が出たら、その場で机を回し、事例パネルの順序を変えていく。
アップルのCMのようにテンポの速い音楽を使った動画を大画面に流しながら、店舗やアパレルアプリの実績をリズミカルに紹介するなど、「立ち止まりたくなる仕掛け」も盛り込みました。
結果として、展示会ごとのリード数はほぼすべての月で目標を上回り、「営業チームが動きやすい設計だった」と言ってもらえたのは嬉しかったですね。
オウンドメディア
編集方針からUIまで一貫して
もう1つは、大手飲料メーカーとタッグを組んで立ち上げたライフスタイル系のオウンドメディア。これは、当時15〜20名の編集・制作チームが関わる中で、UI/UX全体の設計を担当しました。

プロジェクトのスタートは「メディアを立ち上げたい」という、わりと抽象的な相談から。
編集方針やコンセプトづくりの段階から参加し、「読者が生活のなかで読みたくなる」構成とは?という問いに向き合っていきました。
特に印象的だったのが、スクロール連動型のUI設計です。
各カテゴリに入ったときに、そのカテゴリを示すカードが追従する構造を導入しました。
今では一般的になりつつあるこのUIも、当時としてはあまり前例がなく、かなり実験的な取り組みでした。
NIKKEI BP Marketing Awards イノベーティブ部門最優秀賞受賞を取り、クライアントからも「世界観が伝わる」「回遊性が高く、継続率が高い」と評価をいただきました。UI設計が賞を受けたことも、自信につながったプロジェクトのひとつです。
0→1の立ち上げ
他にも、1人目デザイナーとして入ったスタートアップのCI設計や、営業資料・Web・プロダクトUI・LPなど、すべてのクリエイティブを整える案件にも多く携わってきました。
面白いのは、「なんかバラバラしてきたから、一度見直したい」という相談が多いこと。
ブランドって、一度決めて終わりではなく、常に事業の変化や組織構造に引っ張られて揺れていくものなんですよね。
僕が入ることで、「今このタイミングで整えておいた方がいいポイント」を言語化・視覚化し、必要に応じて構造から再設計する。そういった“整流フェーズ”での支援も、ここ数年は増えてきました。
得意な対応範囲
—横断的に“全部”見られること。それが、私の強みです。
プロダクトのUI設計はもちろん、営業資料、広告、LP、展示会のブース設計、SNSや動画、インナーブランディングまで── お客さんと接点を持つあらゆる場所に関わってきました。タッチポイントが増えるほど、ブランドの一貫性は崩れやすくなる。だからこそ、それらを“つなぐ視点”を持って関われることに価値があると思っています。
この感覚は、キャリア初期に経験した「ゼロからのサービス立ち上げ」で自然と身についたものです。プロダクトもマーケも営業資料も、何も揃っていない状態から、一つひとつ作り上げていく中で、「ユーザーの最初の接点はどこか」「誰にとっての導線になっているか」を常に考えるようになりました。
また、代理店と事業会社、両方の立場を経験したことで、アウトプットだけでなく“社内の動かし方”や“現場の納得の作り方”も意識できるようになりました。
代理店にいた頃は、スピード感と発想力、そしてプレゼン力が重視されました。求められるのは、常に「答えを出す人」であること。一方で事業会社に移ってみると、それとはまったく違う景色が広がっていたんです。
になる。むしろ、「良いものだから通る」と思っているだけでは進まない現実がありました。
そうした環境の中で、自分がデザイナーであると同時に「社内政治を読む感覚」も求められることを実感しました。
現在はフリーランスという立場で、いろんな企業の中に入る形で仕事をしていますが、いちばん信頼されるのは「誰とでも会話ができて、現場の構造を把握して動ける人」だと感じています。
「どこが詰まっているのか?」「誰が言い出せずにいるのか?」
そういった“静かな空気”を察知しながら、バランスよく調整していく。
それが、今の自分の仕事の本質だと思っています。
3. 今後の展望
正直なところ、今の時点で明確に「こうしたい」と決めているわけではないんです。
むしろ、これから数年かけて自分にとって一番フィットする働き方や関わり方を探っていきたい、という感覚に近いかもしれません。
いまはフリーランスとして、複数のクライアントとやり取りしていますが、ずっと複数案件を抱えていたいというわけでもなくて。
いずれは、1社か2社にぐっと深く入り込んで、腰を据えてコミットするような形もやってみたいなと思っています。

その判断を急いでいないのは、ツールも環境も日々変化しているからです。
変化が早い世界なので、自分もアップデートを止めずに、常に「今の自分がどう在るのがベストか」を考え続けたいと思っています。
一つだけはっきりしているのは、「共創できる環境で働きたい」ということです。
デザイナーに対してトップダウンで指示を出すというよりも、フラットに対話しながら、「こういうのもアリかも」「これって本質的にはどうだろう」といった視点で一緒に考えられる関係性が好きですし、そういうチームであれば、いくらでもサポートしたいと思えます。
今後どんなクライアントやプロジェクトと出会うかはまだわかりませんが、
“やるべきこと”ではなく、“合うやり方”を探していく感覚を大切にしながら、これからも変わり続けていきたいと思っています。
4. まとめ
Ishibashiさんの話を聞いて印象的だったのは、「デザイナーは表現者ではなく、相手の“普通”を徹底する役割だ」という言葉です。
展示会ブースの導線ひとつとっても、「営業が声をかけやすい位置かどうか」「ユーザーが立ち止まるかどうか」といった観察と調整を徹底し、現場でPDCAを回す姿勢。オウンドメディアの設計では、単なる見た目ではなく「誰にとっての自然な動線か」という視点でUIを設計してきた経験。どちらの事例にも共通するのは、「伝わるかどうか」を感覚ではなく構造で捉えている点でした。
また、代理店と事業会社の両方を経験しているからこそ、「クオリティの高いアウトプットを出す」だけでなく、「社内の納得をつくる」「誰にどう伝えると進むか」を考える視点も持ち合わせています。
現在はフリーランスとして、ゼロイチの立ち上げや既存ブランドの再設計など、さまざまなフェーズに関わりながら、タッチポイントを横断的に整える仕事を担っています。単に「見せ方を整える」のではなく、「どの部門にも自然につながる設計をする」。そんな実践力が、Ishibashiさんの仕事の軸にあると感じました。
5. こういったクライアントにおすすめ
Ishibashiさんが特に力を発揮するのは、「何をどう伝えるべきか」がまだ明確でないフェーズです。デザインやブランドに関する言語化が追いついていない、もしくは複数のチャネルでの一貫性に課題を感じているクライアントです。
以下の課題を持つようなクライアントにIshibashiさんをお勧めします。
MVVやブランドの考え方が社内にうまく浸透していないクライアント
現在のデザインが、事業戦略や組織構造とうまく噛み合っていないと感じているクライアント
初めてデザイナーを迎える、あるいはデザイン体制を拡大したいと考えているクライアント
スタートアップや中堅規模で、新たなフェーズに向けてリブランディングを検討しているクライアント
最後までご覧いただきありがとうございます。
Ishibashiさんへのご相談はもちろん、そのほかデザイン業務についてご相談がございましたらお気軽にこちらよりご予約ください。
一覧に戻る
Related interview
関連するインタビュー

クリエイティブディレクター
【JOOiデザイナーインタビュー】”相手の普通”を徹底し、成果に変えるデザインするIshibashiさん
投稿日:
2025/07/17
事業会社と代理店、両方を経験したIshibashiさんのブランド設計
本記事では、JOOiに在籍しているIshibashiさんをご紹介します。
Ishibashiさんは企業のビジョンや価値観といった抽象度の高い要素を言語化し、それをプロダクトやクリエイティブに落とし込んでいます。
ブランディングの上流工程から、UI/UX・マーケティング関連・コーポレート関連・営業関連など具体的なアウトプットまで、一貫してデザインを設計することができます。
このようなスキルや価値観がどういったキャリアで培われたのかなどインタビューの内容を本記事にまとめております。ぜひ最後までご覧ください。
1. キャリア
プロフィール

広告代理店、制作会社、事業会社と複数の立場を経験し、現在はフリーランスのクリエイティブディレクター/デザイナーとして活動しています。
過去には、月間1,500万PV・年商28億円規模のプラットフォームを運営する企業にて、マーケティング部長〜執行役員を歴任。ブランディング、UI/UX、コンテンツ企画、SNS運用まで、全体のコミュニケーション設計を担当してきました。
SaaS企業での展示会ブース設計やプロモーション設計、Web制作会社での事業部立ち上げなど立ち上げ・再設計フェーズに強みがあります。
現在は、スタートアップや中堅企業の“1人目デザイナー”として、ブランド戦略やプロダクト開発支援を中心に、多面的に関わっています。
現在行っていること
今は、フリーランスのクリエイティブディレクター/デザイナーとして、企業のブランド設計やUI/UXデザイン、マーケティング支援などをしています。スタートアップや中小企業の「1人目・2人目デザイナー」として入るケースも多く、ブランドの“ゼロイチ”を一緒につくるようなプロジェクトが中心です。
たとえば、「会社としてMVVはあるけど、それがビジュアルやトーンに落ちきっていない」とか、「営業資料とサービスサイトのトンマナがズレていて、社内外に一貫性がない」など、組織の中で「伝える設計」が曖昧になっている状態を整える、という仕事が多いです。
また、プロダクトに関わるだけでなく、展示会ブースやパンフレット、動画など「顧客とのタッチポイントすべて」に関与することも多いです。なので、ある意味「社外のクリエイティブ戦略室」みたいな立ち回りになることが多いかもしれません。
デザイナーを目指した理由
—アメリカでの幼少期の経験
「絵を描いたらお小遣いがもらえた」——これが僕の原体験です。
アメリカで小学生の頃、ノートの切れ端にロボットやキャラクターを描いて、それを友達にあげていたら、「これ、あげるよ」ってお菓子をくれたり、小銭をくれたりしたんです。完全に商売の意図はなかったんですけど(笑)
その瞬間、「あれ、これって価値になるんだ」って思ったんですよね。しかも、少しずつ“価格帯”が見えてくる。
人気キャラクターは高い、オリジナルはちょっと安いとか。
自分で何が売れるかを観察して、単価を決めて、納期を守るみたいなことを、今思えば自然にやっていた。その時の感覚は、今の「ブランド設計」に直結していると思います。
事業会社と代理店の違い
—“広く浅く”と“深く長く”——デザイナーとしての両面の学び
代理店と事業会社、どちらも経験してみて、やっぱり立ち回り方はだいぶ変わったなと思います。
代理店は、いろんなプロジェクトに横で関わるようなイメージですね。幅広く、いろんな業界・案件をスピード感もって触っていく感じでした。とにかくアウトプットを出すことが前提で、提案の質やスピードが求められていたと思います。
一方で、事業会社では縦に深く入っていくことが求められました。 僕がいた会社では、一つのサービスに対して営業、インサイドセールス、マーケ、開発、経理まで、本当にたくさんの部署と連携しながら動いていました。
そこで実感したのは、「これは誰の視点を通すべきか」とか「どこを説得すればプロジェクトが前に進むのか」というバランス感覚の大切さです。
言ってしまえばちょっと“政治的”な配慮も必要になってくる。 いろんなステークホルダーのことを考えて、みんなに納得してもらえる形にしていくというのは、インハウスだからこそ身についた感覚だと思います。
それぞれに良さがあって、どちらが正解という話ではないんですが、今の自分がフリーランスとして関われているのは、両方の経験があったからだなと思っています。
2. 制作物・実績
これまでたくさんのプロジェクトに関わってきました。今回はその中でも印象に残っている実績を具体的に2つ紹介させてください。
1つは、あるSaaS企業での展示会ブースの設計。もう1つは、大手飲料メーカーと立ち上げたオウンドメディアのデザインです。
展示会ブース
見せるデザインではなく、“成果を出す空間”をつくる
展示会の目的は、言うまでもなく「リードを獲得すること」です。
僕が関わったプロジェクトでは、月間300〜400件のリード獲得をKPIとして掲げていて、展示会ごとに何百件という成果が求められる状況でした。

当時、社内にはまだブース設計の専門部署はなく、マーケティング担当者と2〜3名でチームを組んで、構成・導線・演出・動画・パンフレットなど、すべてをゼロから設計しました。
特にこだわったのは、“現場でPDCAを回せる設計”です。
たとえば、ブース内の机やディスプレイの位置はすべて可動式にしました。
展示会1日目の終わりに「ここ、全然立ち止まってもらえないよね」「この角度、営業が声かけづらいね」といった声が出たら、その場で机を回し、事例パネルの順序を変えていく。
アップルのCMのようにテンポの速い音楽を使った動画を大画面に流しながら、店舗やアパレルアプリの実績をリズミカルに紹介するなど、「立ち止まりたくなる仕掛け」も盛り込みました。
結果として、展示会ごとのリード数はほぼすべての月で目標を上回り、「営業チームが動きやすい設計だった」と言ってもらえたのは嬉しかったですね。
オウンドメディア
編集方針からUIまで一貫して
もう1つは、大手飲料メーカーとタッグを組んで立ち上げたライフスタイル系のオウンドメディア。これは、当時15〜20名の編集・制作チームが関わる中で、UI/UX全体の設計を担当しました。

プロジェクトのスタートは「メディアを立ち上げたい」という、わりと抽象的な相談から。
編集方針やコンセプトづくりの段階から参加し、「読者が生活のなかで読みたくなる」構成とは?という問いに向き合っていきました。
特に印象的だったのが、スクロール連動型のUI設計です。
各カテゴリに入ったときに、そのカテゴリを示すカードが追従する構造を導入しました。
今では一般的になりつつあるこのUIも、当時としてはあまり前例がなく、かなり実験的な取り組みでした。
NIKKEI BP Marketing Awards イノベーティブ部門最優秀賞受賞を取り、クライアントからも「世界観が伝わる」「回遊性が高く、継続率が高い」と評価をいただきました。UI設計が賞を受けたことも、自信につながったプロジェクトのひとつです。
0→1の立ち上げ
他にも、1人目デザイナーとして入ったスタートアップのCI設計や、営業資料・Web・プロダクトUI・LPなど、すべてのクリエイティブを整える案件にも多く携わってきました。
面白いのは、「なんかバラバラしてきたから、一度見直したい」という相談が多いこと。
ブランドって、一度決めて終わりではなく、常に事業の変化や組織構造に引っ張られて揺れていくものなんですよね。
僕が入ることで、「今このタイミングで整えておいた方がいいポイント」を言語化・視覚化し、必要に応じて構造から再設計する。そういった“整流フェーズ”での支援も、ここ数年は増えてきました。
得意な対応範囲
—横断的に“全部”見られること。それが、私の強みです。
プロダクトのUI設計はもちろん、営業資料、広告、LP、展示会のブース設計、SNSや動画、インナーブランディングまで── お客さんと接点を持つあらゆる場所に関わってきました。タッチポイントが増えるほど、ブランドの一貫性は崩れやすくなる。だからこそ、それらを“つなぐ視点”を持って関われることに価値があると思っています。
この感覚は、キャリア初期に経験した「ゼロからのサービス立ち上げ」で自然と身についたものです。プロダクトもマーケも営業資料も、何も揃っていない状態から、一つひとつ作り上げていく中で、「ユーザーの最初の接点はどこか」「誰にとっての導線になっているか」を常に考えるようになりました。
また、代理店と事業会社、両方の立場を経験したことで、アウトプットだけでなく“社内の動かし方”や“現場の納得の作り方”も意識できるようになりました。
代理店にいた頃は、スピード感と発想力、そしてプレゼン力が重視されました。求められるのは、常に「答えを出す人」であること。一方で事業会社に移ってみると、それとはまったく違う景色が広がっていたんです。
になる。むしろ、「良いものだから通る」と思っているだけでは進まない現実がありました。
そうした環境の中で、自分がデザイナーであると同時に「社内政治を読む感覚」も求められることを実感しました。
現在はフリーランスという立場で、いろんな企業の中に入る形で仕事をしていますが、いちばん信頼されるのは「誰とでも会話ができて、現場の構造を把握して動ける人」だと感じています。
「どこが詰まっているのか?」「誰が言い出せずにいるのか?」
そういった“静かな空気”を察知しながら、バランスよく調整していく。
それが、今の自分の仕事の本質だと思っています。
3. 今後の展望
正直なところ、今の時点で明確に「こうしたい」と決めているわけではないんです。
むしろ、これから数年かけて自分にとって一番フィットする働き方や関わり方を探っていきたい、という感覚に近いかもしれません。
いまはフリーランスとして、複数のクライアントとやり取りしていますが、ずっと複数案件を抱えていたいというわけでもなくて。
いずれは、1社か2社にぐっと深く入り込んで、腰を据えてコミットするような形もやってみたいなと思っています。

その判断を急いでいないのは、ツールも環境も日々変化しているからです。
変化が早い世界なので、自分もアップデートを止めずに、常に「今の自分がどう在るのがベストか」を考え続けたいと思っています。
一つだけはっきりしているのは、「共創できる環境で働きたい」ということです。
デザイナーに対してトップダウンで指示を出すというよりも、フラットに対話しながら、「こういうのもアリかも」「これって本質的にはどうだろう」といった視点で一緒に考えられる関係性が好きですし、そういうチームであれば、いくらでもサポートしたいと思えます。
今後どんなクライアントやプロジェクトと出会うかはまだわかりませんが、
“やるべきこと”ではなく、“合うやり方”を探していく感覚を大切にしながら、これからも変わり続けていきたいと思っています。
4. まとめ
Ishibashiさんの話を聞いて印象的だったのは、「デザイナーは表現者ではなく、相手の“普通”を徹底する役割だ」という言葉です。
展示会ブースの導線ひとつとっても、「営業が声をかけやすい位置かどうか」「ユーザーが立ち止まるかどうか」といった観察と調整を徹底し、現場でPDCAを回す姿勢。オウンドメディアの設計では、単なる見た目ではなく「誰にとっての自然な動線か」という視点でUIを設計してきた経験。どちらの事例にも共通するのは、「伝わるかどうか」を感覚ではなく構造で捉えている点でした。
また、代理店と事業会社の両方を経験しているからこそ、「クオリティの高いアウトプットを出す」だけでなく、「社内の納得をつくる」「誰にどう伝えると進むか」を考える視点も持ち合わせています。
現在はフリーランスとして、ゼロイチの立ち上げや既存ブランドの再設計など、さまざまなフェーズに関わりながら、タッチポイントを横断的に整える仕事を担っています。単に「見せ方を整える」のではなく、「どの部門にも自然につながる設計をする」。そんな実践力が、Ishibashiさんの仕事の軸にあると感じました。
5. こういったクライアントにおすすめ
Ishibashiさんが特に力を発揮するのは、「何をどう伝えるべきか」がまだ明確でないフェーズです。デザインやブランドに関する言語化が追いついていない、もしくは複数のチャネルでの一貫性に課題を感じているクライアントです。
以下の課題を持つようなクライアントにIshibashiさんをお勧めします。
MVVやブランドの考え方が社内にうまく浸透していないクライアント
現在のデザインが、事業戦略や組織構造とうまく噛み合っていないと感じているクライアント
初めてデザイナーを迎える、あるいはデザイン体制を拡大したいと考えているクライアント
スタートアップや中堅規模で、新たなフェーズに向けてリブランディングを検討しているクライアント
最後までご覧いただきありがとうございます。
Ishibashiさんへのご相談はもちろん、そのほかデザイン業務についてご相談がございましたらお気軽にこちらよりご予約ください。
一覧に戻る
Related interview
関連するインタビュー

クリエイティブディレクター
【JOOiデザイナーインタビュー】”相手の普通”を徹底し、成果に変えるデザインするIshibashiさん
投稿日:
2025/07/17
事業会社と代理店、両方を経験したIshibashiさんのブランド設計
本記事では、JOOiに在籍しているIshibashiさんをご紹介します。
Ishibashiさんは企業のビジョンや価値観といった抽象度の高い要素を言語化し、それをプロダクトやクリエイティブに落とし込んでいます。
ブランディングの上流工程から、UI/UX・マーケティング関連・コーポレート関連・営業関連など具体的なアウトプットまで、一貫してデザインを設計することができます。
このようなスキルや価値観がどういったキャリアで培われたのかなどインタビューの内容を本記事にまとめております。ぜひ最後までご覧ください。
1. キャリア
プロフィール

広告代理店、制作会社、事業会社と複数の立場を経験し、現在はフリーランスのクリエイティブディレクター/デザイナーとして活動しています。
過去には、月間1,500万PV・年商28億円規模のプラットフォームを運営する企業にて、マーケティング部長〜執行役員を歴任。ブランディング、UI/UX、コンテンツ企画、SNS運用まで、全体のコミュニケーション設計を担当してきました。
SaaS企業での展示会ブース設計やプロモーション設計、Web制作会社での事業部立ち上げなど立ち上げ・再設計フェーズに強みがあります。
現在は、スタートアップや中堅企業の“1人目デザイナー”として、ブランド戦略やプロダクト開発支援を中心に、多面的に関わっています。
現在行っていること
今は、フリーランスのクリエイティブディレクター/デザイナーとして、企業のブランド設計やUI/UXデザイン、マーケティング支援などをしています。スタートアップや中小企業の「1人目・2人目デザイナー」として入るケースも多く、ブランドの“ゼロイチ”を一緒につくるようなプロジェクトが中心です。
たとえば、「会社としてMVVはあるけど、それがビジュアルやトーンに落ちきっていない」とか、「営業資料とサービスサイトのトンマナがズレていて、社内外に一貫性がない」など、組織の中で「伝える設計」が曖昧になっている状態を整える、という仕事が多いです。
また、プロダクトに関わるだけでなく、展示会ブースやパンフレット、動画など「顧客とのタッチポイントすべて」に関与することも多いです。なので、ある意味「社外のクリエイティブ戦略室」みたいな立ち回りになることが多いかもしれません。
デザイナーを目指した理由
—アメリカでの幼少期の経験
「絵を描いたらお小遣いがもらえた」——これが僕の原体験です。
アメリカで小学生の頃、ノートの切れ端にロボットやキャラクターを描いて、それを友達にあげていたら、「これ、あげるよ」ってお菓子をくれたり、小銭をくれたりしたんです。完全に商売の意図はなかったんですけど(笑)
その瞬間、「あれ、これって価値になるんだ」って思ったんですよね。しかも、少しずつ“価格帯”が見えてくる。
人気キャラクターは高い、オリジナルはちょっと安いとか。
自分で何が売れるかを観察して、単価を決めて、納期を守るみたいなことを、今思えば自然にやっていた。その時の感覚は、今の「ブランド設計」に直結していると思います。
事業会社と代理店の違い
—“広く浅く”と“深く長く”——デザイナーとしての両面の学び
代理店と事業会社、どちらも経験してみて、やっぱり立ち回り方はだいぶ変わったなと思います。
代理店は、いろんなプロジェクトに横で関わるようなイメージですね。幅広く、いろんな業界・案件をスピード感もって触っていく感じでした。とにかくアウトプットを出すことが前提で、提案の質やスピードが求められていたと思います。
一方で、事業会社では縦に深く入っていくことが求められました。 僕がいた会社では、一つのサービスに対して営業、インサイドセールス、マーケ、開発、経理まで、本当にたくさんの部署と連携しながら動いていました。
そこで実感したのは、「これは誰の視点を通すべきか」とか「どこを説得すればプロジェクトが前に進むのか」というバランス感覚の大切さです。
言ってしまえばちょっと“政治的”な配慮も必要になってくる。 いろんなステークホルダーのことを考えて、みんなに納得してもらえる形にしていくというのは、インハウスだからこそ身についた感覚だと思います。
それぞれに良さがあって、どちらが正解という話ではないんですが、今の自分がフリーランスとして関われているのは、両方の経験があったからだなと思っています。
2. 制作物・実績
これまでたくさんのプロジェクトに関わってきました。今回はその中でも印象に残っている実績を具体的に2つ紹介させてください。
1つは、あるSaaS企業での展示会ブースの設計。もう1つは、大手飲料メーカーと立ち上げたオウンドメディアのデザインです。
展示会ブース
見せるデザインではなく、“成果を出す空間”をつくる
展示会の目的は、言うまでもなく「リードを獲得すること」です。
僕が関わったプロジェクトでは、月間300〜400件のリード獲得をKPIとして掲げていて、展示会ごとに何百件という成果が求められる状況でした。

当時、社内にはまだブース設計の専門部署はなく、マーケティング担当者と2〜3名でチームを組んで、構成・導線・演出・動画・パンフレットなど、すべてをゼロから設計しました。
特にこだわったのは、“現場でPDCAを回せる設計”です。
たとえば、ブース内の机やディスプレイの位置はすべて可動式にしました。
展示会1日目の終わりに「ここ、全然立ち止まってもらえないよね」「この角度、営業が声かけづらいね」といった声が出たら、その場で机を回し、事例パネルの順序を変えていく。
アップルのCMのようにテンポの速い音楽を使った動画を大画面に流しながら、店舗やアパレルアプリの実績をリズミカルに紹介するなど、「立ち止まりたくなる仕掛け」も盛り込みました。
結果として、展示会ごとのリード数はほぼすべての月で目標を上回り、「営業チームが動きやすい設計だった」と言ってもらえたのは嬉しかったですね。
オウンドメディア
編集方針からUIまで一貫して
もう1つは、大手飲料メーカーとタッグを組んで立ち上げたライフスタイル系のオウンドメディア。これは、当時15〜20名の編集・制作チームが関わる中で、UI/UX全体の設計を担当しました。

プロジェクトのスタートは「メディアを立ち上げたい」という、わりと抽象的な相談から。
編集方針やコンセプトづくりの段階から参加し、「読者が生活のなかで読みたくなる」構成とは?という問いに向き合っていきました。
特に印象的だったのが、スクロール連動型のUI設計です。
各カテゴリに入ったときに、そのカテゴリを示すカードが追従する構造を導入しました。
今では一般的になりつつあるこのUIも、当時としてはあまり前例がなく、かなり実験的な取り組みでした。
NIKKEI BP Marketing Awards イノベーティブ部門最優秀賞受賞を取り、クライアントからも「世界観が伝わる」「回遊性が高く、継続率が高い」と評価をいただきました。UI設計が賞を受けたことも、自信につながったプロジェクトのひとつです。
0→1の立ち上げ
他にも、1人目デザイナーとして入ったスタートアップのCI設計や、営業資料・Web・プロダクトUI・LPなど、すべてのクリエイティブを整える案件にも多く携わってきました。
面白いのは、「なんかバラバラしてきたから、一度見直したい」という相談が多いこと。
ブランドって、一度決めて終わりではなく、常に事業の変化や組織構造に引っ張られて揺れていくものなんですよね。
僕が入ることで、「今このタイミングで整えておいた方がいいポイント」を言語化・視覚化し、必要に応じて構造から再設計する。そういった“整流フェーズ”での支援も、ここ数年は増えてきました。
得意な対応範囲
—横断的に“全部”見られること。それが、私の強みです。
プロダクトのUI設計はもちろん、営業資料、広告、LP、展示会のブース設計、SNSや動画、インナーブランディングまで── お客さんと接点を持つあらゆる場所に関わってきました。タッチポイントが増えるほど、ブランドの一貫性は崩れやすくなる。だからこそ、それらを“つなぐ視点”を持って関われることに価値があると思っています。
この感覚は、キャリア初期に経験した「ゼロからのサービス立ち上げ」で自然と身についたものです。プロダクトもマーケも営業資料も、何も揃っていない状態から、一つひとつ作り上げていく中で、「ユーザーの最初の接点はどこか」「誰にとっての導線になっているか」を常に考えるようになりました。
また、代理店と事業会社、両方の立場を経験したことで、アウトプットだけでなく“社内の動かし方”や“現場の納得の作り方”も意識できるようになりました。
代理店にいた頃は、スピード感と発想力、そしてプレゼン力が重視されました。求められるのは、常に「答えを出す人」であること。一方で事業会社に移ってみると、それとはまったく違う景色が広がっていたんです。
になる。むしろ、「良いものだから通る」と思っているだけでは進まない現実がありました。
そうした環境の中で、自分がデザイナーであると同時に「社内政治を読む感覚」も求められることを実感しました。
現在はフリーランスという立場で、いろんな企業の中に入る形で仕事をしていますが、いちばん信頼されるのは「誰とでも会話ができて、現場の構造を把握して動ける人」だと感じています。
「どこが詰まっているのか?」「誰が言い出せずにいるのか?」
そういった“静かな空気”を察知しながら、バランスよく調整していく。
それが、今の自分の仕事の本質だと思っています。
3. 今後の展望
正直なところ、今の時点で明確に「こうしたい」と決めているわけではないんです。
むしろ、これから数年かけて自分にとって一番フィットする働き方や関わり方を探っていきたい、という感覚に近いかもしれません。
いまはフリーランスとして、複数のクライアントとやり取りしていますが、ずっと複数案件を抱えていたいというわけでもなくて。
いずれは、1社か2社にぐっと深く入り込んで、腰を据えてコミットするような形もやってみたいなと思っています。

その判断を急いでいないのは、ツールも環境も日々変化しているからです。
変化が早い世界なので、自分もアップデートを止めずに、常に「今の自分がどう在るのがベストか」を考え続けたいと思っています。
一つだけはっきりしているのは、「共創できる環境で働きたい」ということです。
デザイナーに対してトップダウンで指示を出すというよりも、フラットに対話しながら、「こういうのもアリかも」「これって本質的にはどうだろう」といった視点で一緒に考えられる関係性が好きですし、そういうチームであれば、いくらでもサポートしたいと思えます。
今後どんなクライアントやプロジェクトと出会うかはまだわかりませんが、
“やるべきこと”ではなく、“合うやり方”を探していく感覚を大切にしながら、これからも変わり続けていきたいと思っています。
4. まとめ
Ishibashiさんの話を聞いて印象的だったのは、「デザイナーは表現者ではなく、相手の“普通”を徹底する役割だ」という言葉です。
展示会ブースの導線ひとつとっても、「営業が声をかけやすい位置かどうか」「ユーザーが立ち止まるかどうか」といった観察と調整を徹底し、現場でPDCAを回す姿勢。オウンドメディアの設計では、単なる見た目ではなく「誰にとっての自然な動線か」という視点でUIを設計してきた経験。どちらの事例にも共通するのは、「伝わるかどうか」を感覚ではなく構造で捉えている点でした。
また、代理店と事業会社の両方を経験しているからこそ、「クオリティの高いアウトプットを出す」だけでなく、「社内の納得をつくる」「誰にどう伝えると進むか」を考える視点も持ち合わせています。
現在はフリーランスとして、ゼロイチの立ち上げや既存ブランドの再設計など、さまざまなフェーズに関わりながら、タッチポイントを横断的に整える仕事を担っています。単に「見せ方を整える」のではなく、「どの部門にも自然につながる設計をする」。そんな実践力が、Ishibashiさんの仕事の軸にあると感じました。
5. こういったクライアントにおすすめ
Ishibashiさんが特に力を発揮するのは、「何をどう伝えるべきか」がまだ明確でないフェーズです。デザインやブランドに関する言語化が追いついていない、もしくは複数のチャネルでの一貫性に課題を感じているクライアントです。
以下の課題を持つようなクライアントにIshibashiさんをお勧めします。
MVVやブランドの考え方が社内にうまく浸透していないクライアント
現在のデザインが、事業戦略や組織構造とうまく噛み合っていないと感じているクライアント
初めてデザイナーを迎える、あるいはデザイン体制を拡大したいと考えているクライアント
スタートアップや中堅規模で、新たなフェーズに向けてリブランディングを検討しているクライアント
最後までご覧いただきありがとうございます。
Ishibashiさんへのご相談はもちろん、そのほかデザイン業務についてご相談がございましたらお気軽にこちらよりご予約ください。
一覧に戻る
Related interview
関連するインタビュー